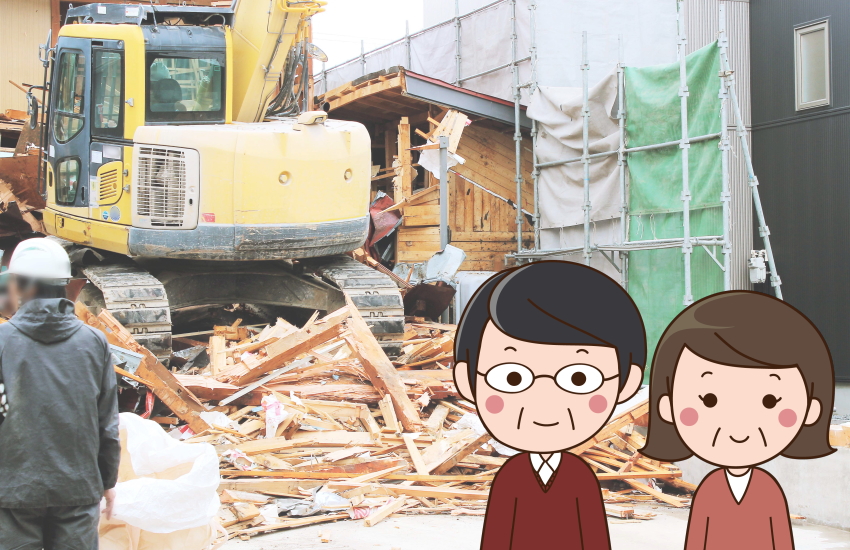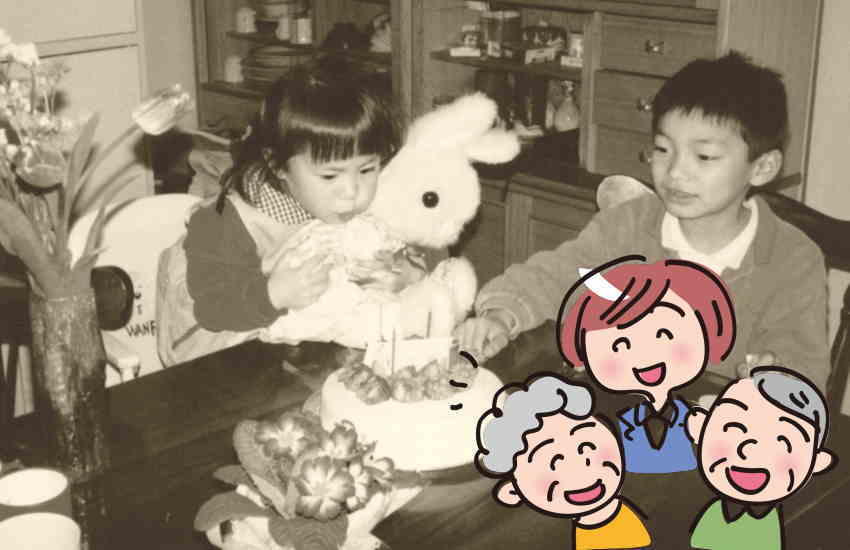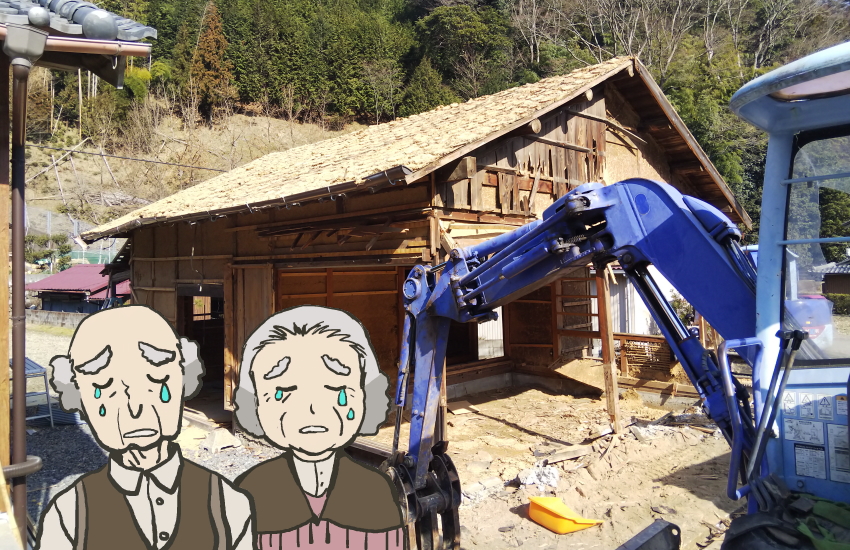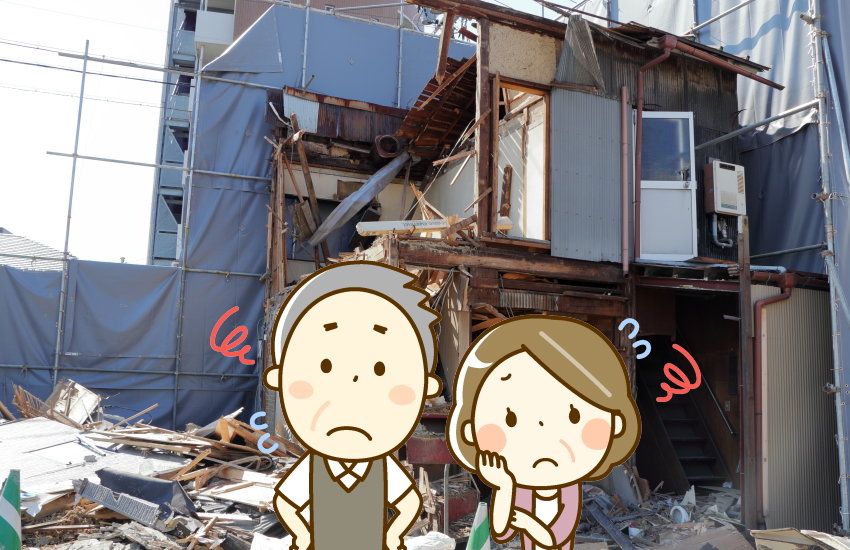
家の解体を検討する際、
「中の物をどこまで片付ければいいのか?」
は多くの方が悩むポイントです。結論から言うと、原則として家の中は完全に空にすることが基本ですが、解体業者との交渉次第で一部の残置物はそのまま解体できる場合もあります。
本記事では、遠方の実家を相続し、限られた時間の中で遺品整理と解体を進めたい方に向けて、
・片付けの判断基準から費用相場
・効率的な進め方
まで徹底解説します。
自分で片付けるか?
業者に依頼するか?
で費用が2倍以上変わるケースもあるため、正しい知識を持つことが重要です。
家の解体でどこまで片づける?の基本ルールを解説

解体工事では原則として建物内を完全に空にする必要があります。
ただし、解体業者によっては追加費用を支払うことで残置物をそのまま処分してくれるケースもあります。
自分で片付けるか?
解体だけでなく片付けまで業者に依頼するか?
それで、総費用が30万円以上変わることも珍しくありません。
また、残置物の種類や量によって解体工事の進行に影響が出るため、事前に業者と詳細を確認することが不可欠です。
片付けの範囲を決める前に、まずは基本的なルールと判断基準を理解しましょう。
「完全に空にする」が原則である3つの理由
解体業者が「完全に空にしてほしい」と求めるのには明確な理由があります。
第一に、建物の解体で発生する廃材(木材、コンクリートなど)と家財道具では、廃棄物の分類が異なるためです。
建設廃材は「産業廃棄物」として処理されますが、家具や家電は「一般廃棄物」に分類されます。
これらを混在させると法律違反になる可能性があり、処分費用も大幅に上がります。
第二の理由は、重機作業の安全性確保です。
タンスや冷蔵庫などが残っていると、重機での取り壊し時に予期せぬ事故や怪我につながるリスクが高まります。
第三に、残置物があると解体工事の作業効率が著しく低下します。
家具を避けながらの作業は時間がかかり、工期の延長や追加の人件費が発生するためです。
こうした理由から、多くの解体業者は事前の完全撤去を標準条件としています。
残していいもの・必ず撤去すべきもの判断チェックリスト
解体時に残せるものと撤去が必須のものを正確に判断することが重要です。以下のチェックリストを参考にしてください。
- 家電製品(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなど)
- 危険物(灯油、ガスボンベ、塗料、農薬など)
- 貴重品・重要書類(現金、通帳、権利証、写真など)
- リサイクル家電(家電リサイクル法対象品目)
- 有害物質を含むもの(蛍光灯、バッテリーなど)
- 木製家具(タンス、食器棚、テーブルなど)
- 布団、衣類などの可燃物
- 食器、小物類
- カーテン、ラグなどの布製品
ただし、「残せる可能性がある」ものでも、追加費用が発生します。
業者によって対応可否が異なるため、必ず見積もり時に確認が必要です。
また、思い出の品や貴重品は解体前に必ず取り出しておきましょう。
解体業者が「そのまま解体OK」と言う場合の注意点
「家財をそのまま残して解体できます」と言う業者も存在します。
ですが、安易に依頼するのは危険です。
このサービスには必ず追加費用が発生し、その金額は業者によって大きく異なります。
相場としては、残置物の量に応じて10万円〜50万円程度の追加料金が一般的です。
しかし、事前の見積もりが曖昧で、後から「想定より物が多かった」として高額請求されるトラブルも報告されています。
また、残置物処分を請け負う業者が、適切な廃棄物処理の許可を持っているか確認することも重要です。
無許可業者に依頼すると、不法投棄などのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
「そのまま解体OK」と言われても、必ず書面で処分費用の内訳と上限額を確認し、一般廃棄物収集運搬業の許可証の提示を求めましょう。
タンス・家具・家電・エアコンなど品目別の判断基準
品目ごとに処分方法と残置の可否が異なるため、正しい判断が必要です。
タンスや食器棚などの大型木製家具は、解体業者によって「可燃物として処分可能」とする場合もあります。
ただし、金属パーツが多い家具は分別が必要になるため、断られるケースも多いです。
家電製品は法律で処分方法が定められており、冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビは家電リサイクル法の対象となります。
これらは家電量販店やメーカーによる回収が義務付けられており、解体業者は原則として処分できません。
エアコンは特に注意が必要で、フロンガス(冷媒)の適切な回収が法律で義務付けられています。
無資格者による取り外しは違法であり、必ず専門業者に依頼する必要があります。
小型家電や布団、衣類などは、一般廃棄物として自治体のゴミ回収に出すのが最も経済的です。
品目ごとの適切な処分方法を知ることで、無駄な費用を抑えられます。
家の解体前の片付けの残置物の処分費用と削減方法

残置物の処分を業者に依頼する場合、4トントラック1台あたり5万円〜10万円が一般的な相場です。
一方、自分で処分すれば市区町村の一般廃棄物として格安で処理でき、数千円〜数万円程度に抑えられます。
処分方法の選択によって費用が大きく変わるため、予算と時間のバランスを考慮した判断が重要です。
解体業者、
遺品整理業者、
不用品回収業者、
自己処分
の4つの選択肢があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、ここでは最新の費用相場と実際に費用を半額以下に抑えるテクニックを解説します。
残置物処分の費用相場(解体業者・遺品整理業者・自己処分)
残置物処分の費用は依頼先によって大きく異なります。
解体業者に一括で依頼する場合、4トントラック1台分で5万円〜10万円が相場です。
この方法は手間が省けますが、解体業者は廃棄物処分の専門ではないため、実際には下請けの処分業者に再委託することが多いです。
ですので、中間マージンが発生します。
遺品整理業者に依頼する場合は、同じ4トントラック1台分で8万円〜15万円程度と割高になりますが、丁寧な仕分けや貴重品の捜索、買取サービスなどが含まれます。
不用品回収業者は4トントラック1台で6万円〜12万円程度で、即日対応や深夜作業にも対応できる柔軟性があります。
自己処分の場合、市区町村の粗大ゴミ回収を利用すれば1点300円〜2,000円程度で済み、総額でも2万円〜5万円程度に抑えられます。
ただし、運搬や分別の手間と時間が必要です。
ゴミ屋敷状態の場合の追加費用と特殊対応
長年放置された実家がゴミ屋敷状態になっている場合、通常の片付けとは異なる特殊な対応が必要になります。
ゴミ屋敷の処分費用は、一般的な住宅の2倍〜3倍が相場で、2トントラック3台〜5台分の搬出で30万円〜80万円程度かかります。
費用が高くなる理由は、害虫駆除や悪臭除去などの特殊清掃が必要になる場合がああるからです。
また、大量のゴミの中から貴重品や重要書類を探す作業に時間がかかり、人件費も増加します。
床が腐食していたり、壁にカビが生えていたりする場合は、清掃費用としてさらに10万円〜30万円程度の追加費用が発生することもあります。
ゴミ屋敷専門の業者に依頼すると、近隣への配慮(養生、臭い対策)や迅速な搬出作業を行ってくれます。
費用は高額ですが、自力での片付けは衛生面や安全面でリスクが高いため、専門業者への依頼を強く推奨します。
費用を半額以下に抑える3つの削減テクニック
残置物処分の費用を大幅に削減するには、戦略的なアプローチが有効です。
第一のテクニックは、「買取サービスの活用」です。
遺品整理業者や不用品回収業者の中には、買取サービスを併設している会社があります。
価値のある家具や家電、骨董品などがあれば、処分費用から買取額を差し引いてもらえるため、実質的な負担が減ります。
第二のテクニックは、「自己処分と業者依頼のハイブリッド方式」です。
衣類や小物など自分で処分できるものは事前に市区町村のゴミ回収に出し、大型家具のみを業者に依頼すれば搬出量が減り費用を半額程度に抑えられます。
第三のテクニックは、「相見積もりによる価格交渉」です。
最低3社から見積もりを取り、条件を提示して価格交渉を行えば、当初の見積もりから10%〜20%の値引きを引き出せることがあります。
ただし、極端に安い業者は不法投棄のリスクがあるため、許可証の確認を怠らないようにしましょう。
見積もり時に確認必須!隠れた追加費用に注意
見積もり時に確認を怠ると、後から高額な追加請求を受けるトラブルが発生します。
特に注意すべきは「基本料金」と「追加料金」の内訳です。
「4トントラック1台5万円」と提示されても、それが「積み放題」なのか「基本料金のみ」なのかで大きく変わります。
基本料金のみの場合、トラックに積みきれない分は追加料金が発生し、最終的に倍額になることもあります。
また、
「2階からの搬出」
「狭い道路での作業」
「エレベーターなしのマンション」
などの条件で追加費用が発生する業者も多いです。
階段作業費として1階ごとに5,000円〜1万円、
狭小地作業費として2万円〜3万円
が加算されることがあります。
さらに、「処分費込み」と言われても、家電リサイクル料金や有害物質の処分費は別途請求される場合があります。
見積もり時には必ず
「これ以上費用が発生する可能性はあるか?」
「追加費用が発生する条件は何か?」
を書面で確認しましょう。
まずは実家のある自治体のホームページをチェックしましょう
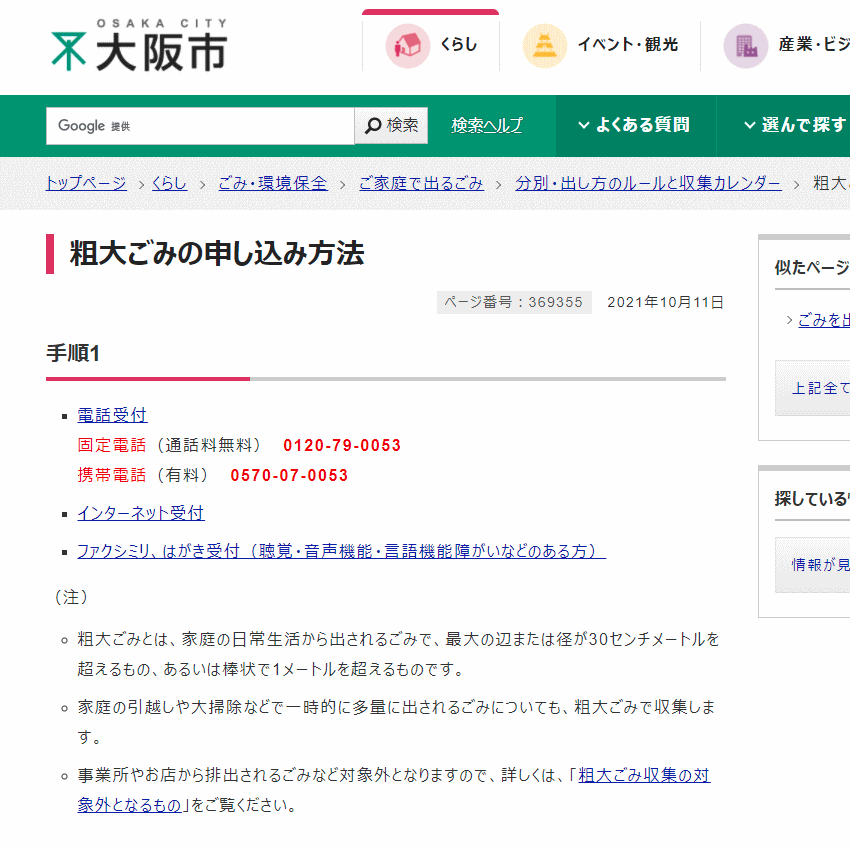
参考:大阪市の粗大ごみ回収
まずは実家のある自治体の不用品回収のやり方をチェックしておきましょう。
不用や粗大ごみは問うやって出すのか?
それにはいくらかかるのか?
そのあたりを調べてからコツコツと少しずつでもいいので解体前にできるだけ実家の片付けを進めておきましょう。
遠方の実家を解体前に効率的に片付ける実践プラン

遠方の実家を片付ける場合、業者への一括依頼が時間とコストの両面で最も効率的です。
何度も往復する交通費や宿泊費を考えると、多少業者費用が高くても総合的には安く済むケースが多いからです。
解体と片付けを同じ業者に依頼するか、別々の専門業者に分けるかで、作業の質と費用が大きく変わります。また、遠方からの依頼では現地確認の回数を最小限にするための段取りが重要です。ここでは、忙しい会社員が最小限の帰省回数で片付けと解体を完結させるための実践的なプランを紹介します。
忙しい会社員向け「最小限の帰省で完結させる」段取り術
遠方の実家の片付けと解体を最小限の帰省回数で完結させるには、事前準備と業者選びが鍵になります。
理想的な帰省回数は2回で、1回目は現地調査と貴重品の確保、2回目は最終確認と鍵の引き渡しです。
1回目の帰省では、写真や動画で家の中と外を詳細に記録し、残置物の量を把握します。
この記録を複数の業者に送ることで、現地訪問なしでの概算見積もりが可能になります。
同時に、貴重品(現金、通帳、印鑑、権利証、思い出の品)は必ずこのタイミングで持ち帰りましょう。
その後、オンラインで業者とやり取りを進め、正式な見積もりと契約を済ませます。
業者の中には、立ち会い不要で作業を完了してくれる会社もあります。
2回目の帰省は、解体工事の開始前または完了後に行い、近隣への挨拶や最終確認をします。
事前にスケジュールを綿密に組むことで、仕事を休む日数を最小限に抑えられます。
片付けと解体の依頼方法には3つのパターンがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
パターン1は「解体業者に一括依頼」で、片付けから解体までを1社に任せる方法です。
メリットは窓口が一本化され、スケジュール調整が楽な点と業者間の責任の所在が明確な点です。
デメリットは、解体業者が片付けを下請けに出すため中間マージンが発生し、費用が割高になる点です。
パターン2は「遺品整理業者+解体業者に分離発注」で、まず遺品整理の専門業者に片付けを依頼し、その後解体業者に工事を依頼します。
メリットは、遺品整理業者が丁寧な仕分けや買取をしてくれるため、貴重品の見落としが少なく、買取額で費用を相殺できる可能性がある点です。
デメリットは、2社との契約や日程調整が必要で手間がかかる点です。
パターン3は「自己片付け+解体業者」で、可能な範囲で自分たちが片付け、大型家具のみを業者に依頼する方法です。
費用は最も安く抑えられますが、時間と労力が大幅にかかります。
「ワンストップ対応業者」vs「分離発注」のコスト・手間の違い
ワンストップ対応業者と分離発注では、コストと手間のバランスが大きく異なります。
ワンストップ対応業者(片付けと解体を一括で請け負う業者)に依頼する場合、費用の目安は30坪の木造住宅で150万円〜250万円程度です。
内訳は、
・残置物処分費が30万円〜50万円
・解体工事費が120万円〜200万円
です。
メリットは、契約が1回で済み、スケジュール調整が不要で、責任の所在が明確な点です。
一方、分離発注(遺品整理業者と解体業者を別々に依頼)の場合、同じ条件で140万円〜230万円程度となり、10万円〜20万円ほど安くなる傾向があります。
これは、各専門業者が直接作業するため中間マージンが発生しないためです。
ただし、業者間の日程調整や、片付け完了の確認、2度の立ち会いなどの手間がかかります。
時間に余裕があり費用を抑えたい人は分離発注、
多忙で手間を最小限にしたい人はワンストップ対応を選ぶとよいでしょう。
遠方対応可能な優良業者の選び方と見積もり取得のコツ
遠方の実家の片付けと解体を依頼する際、業者選びには特別な注意が必要です。
まず、「遠方対応実績」の豊富な業者を選びましょう。
オンラインでの見積もりや立ち会い不要での作業、写真・動画での進捗報告などに対応できる業者が理想的です。
業者のホームページで「遠方からの依頼」の事例紹介があるかを確認すると良いでしょう。
見積もりを取得する際のコツは、まず家の写真と動画を撮影し、間取り図とともに複数業者に送ることです。
写真は、
・各部屋の全景
・残置物の量がわかるアングル
・外観と周辺道路の状況
を含めます。
これにより、現地訪問なしで精度の高い概算見積もりが可能になります。
また、
「立ち会いなしでの作業は可能か?」
「作業完了の報告方法」
「追加費用が発生する条件」
を必ず確認しましょう。
優良業者は、作業前・作業中・作業後の写真報告を丁寧に行い、透明性の高い対応をしてくれます。
—
実家の解体で使える補助金活用と失敗しない業者選びのポイント

解体工事には自治体から最大100万円程度の補助金を受けられる制度があります。
ただし、補助金の申請には
「片付け完了後」
「解体工事前」
というタイミングの制約があるため、事前の計画が重要です。
また、補助金を受けるためには、建物が一定の条件(指定地域、築年数、耐震基準など)を満たしている必要があります。
一方、業者選びを誤ると、不法投棄や高額な追加請求などのトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
ここでは、補助金を最大限活用する方法と、悪質業者を見抜くチェックポイント、契約時の注意事項を解説します。
解体補助金の申請条件と片付け・解体のベストタイミング
解体補助金を受けるためには、片付けと解体のタイミングを正しく理解することが不可欠です。
多くの自治体では、
「建物が空き家状態であること」
「解体工事着工前に申請すること」
が条件となっています。
そのため、片付けは解体工事の前に完了させる必要がありますが、補助金の申請自体は片付け完了後・解体着工前に行います。
具体的な流れは次の通りです。
まず、自治体の窓口で補助金制度の対象かを確認し、必要書類(建物の登記簿謄本、固定資産税評価証明書など)を準備します。
次に、片付けを完了させ、建物内を空にした状態で写真を撮影します。
その後、解体業者から見積書を取得し、補助金の申請書と一緒に自治体に提出します。申請が承認されてから解体工事に着手し、工事完了後に完了報告書と領収書を提出することで補助金が交付されます。申請から交付まで数ヶ月かかるため、早めの行動が重要です。
自治体別の補助金制度と申請の流れ(主要エリア別)
解体補助金の制度は自治体によって大きく異なります。
東京都内では、老朽化した木造住宅の解体に対して、工事費の3分の1から2分の1(上限50万円〜100万円)を補助する区が多いです。
例えば、世田谷区では「老朽建築物除却工事助成」として上限100万円、
品川区では「老朽建築物除却工事助成」として上限50万円の補助があります。
大阪市では「空家等除却促進補助金」として上限50万円、
名古屋市では「老朽危険空家等除却費補助金」として上限50万円の制度があります。
申請の流れは概ね共通しており、
①事前相談
②交付申請
③承認
④工事着工
⑤完了報告
⑥補助金交付
という6ステップです。
注意点として、多くの自治体では年度ごとに予算が決まっており、先着順や抽選制となっています。
そのため、年度初めの早い時期に申請することが採択率を高めるコツです。
自分の実家がある自治体のホームページで「解体 補助金」または「空き家 除却 助成」で検索し、最新情報を確認しましょう。
悪質業者を見抜く5つのチェックポイント
解体業者の中には、不法投棄や高額請求を行う悪質業者も存在します。
トラブルを避けるために、以下の5つのチェックポイントを必ず確認しましょう。
- 建設業許可または解体工事業登録の有無
500万円以上の解体工事には建設業許可が、それ以下でも解体工事業の登録が必要です。
許可証や登録証のコピーを見せてもらい、有効期限を確認しましょう。 - 産業廃棄物収集運搬業の許可
解体で出た廃材を適切に処分するには、この許可が必要です。
無許可業者は不法投棄のリスクが高いため、必ず確認してください。 - 見積書の詳細度
「一式」表記が多い見積書は要注意です。
優良業者は、「木造部分解体」「基礎撤去」「廃材運搬費」「処分費」など項目を細かく分けて記載します。 - 極端に安い見積もり
相場より著しく安い業者は、後から追加請求をしたり、不法投棄でコストを削減している可能性があります。 - 会社の所在地と実績
会社の所在地が実在するか?
ホームページに施工実績が掲載されているか?
を確認しましょう。
口コミサイトでの評判も参考になります。
契約前に必ず確認すべき見積書の項目と契約書の注意点
契約前に見積書と契約書の内容を詳細に確認することで、後のトラブルを防げます。
見積書で確認すべき項目は、まず「工事費の内訳」です。
仮設工事費(足場、養生)、
解体工事費(建物本体、基礎、外構)、
廃材処分費、
諸経費
などが明確に分かれているかを確認しましょう。
次に「残置物処分費」が含まれているか、別途請求かを確認します。
含まれている場合、処分できる残置物の種類と量の上限も確認が必要です。
さらに、「追加費用の発生条件」を明記してもらいましょう。
地中埋設物(古い浄化槽、廃材など)が見つかった場合の対応と費用についても、事前に取り決めておくことが重要です。
契約書では、
「工事期間」
「支払条件」
「損害賠償責任」
「近隣トラブル時の対応」
を必ず確認します。
特に支払条件は、「着工前に全額」を要求する業者は避け、「着工時30%、完了時70%」のような分割払いができる業者を選びましょう。
契約書は必ず書面で取り交わし、口約束だけで工事を始める業者は絶対に避けてください。
まとめ
家の解体前の片付けは、原則として家の中を完全に空にすることが基本です。
しかし、解体業者によっては追加費用を支払うことで、条件付きで一部の残置物も処分してもらえる場合があります。
依頼先や処分方法の選択によって総費用は大きく変わるため、相見積もりや買取サービスなどを活用し、コストを抑える工夫が重要です。
また、家電リサイクル法に基づく品目や危険物の扱い、業者の許認可や追加費用の明確化など、事前の確認事項も入念に行いましょう。
なお、令和5年の住宅・土地統計調査によれば、日本の空き家数は約899万戸、空き家率は13.8%と過去最高を記録しています。
遠方の実家を相続した場合も、効率的な片付け手順や補助金制度、信頼できる業者選びを意識することで、手間や出費を最小限に抑えて安心して解体まで進められます。
【結論】実家の解体費用を抑えたいなら片付けはできるだけやる
家財道具などを自㏍なお建物内に残したままだと解体費用が割高になる理由がお分かりいただけたでしょうか?
ですので、可能な限り実家の建物内には荷物や家具などは残さないようにするおうがおすすめです。
しかし、室内には家具や家電、洋服などさまざまな物が残っていることでしょう。
行政でも不用品回収は行てくれていますが、費用や手間を考えればこんな風に遺品整理業者に頼むのもお勧めです。
高齢者や女性ならば重い家電や家具などを運びだすのも困難です。
実家の荷物を片付けなくても売却は可能
時間的制約や体力的な制約。
様々な理由で実家の片付けができないかあタも少なくありません。
そこで知っておいてほしいのが、実家の荷物の片づけをしなくてても売却は可能なケースもあることです。
その場合、買主はどうしてもプロの不動産業はになります。
プロの不動産業であれば、家の残置物の処分や解体工事はお手のものです。
それに、一般の方よりもかなり割安に発注できます。
ただし、自分で片付けと解体を行えば一般のエンドユーザーに売却できて、そのほうが高く売れます。
このあたりは、各自の事情によって異なります。
 【解体しての売却値段と解体しない売却値段があまり変わらないこともある】
【解体しての売却値段と解体しない売却値段があまり変わらないこともある】もし解体する実家で売却も考えているなら解体前に現状でのお値段も調べておきましょう。
意外と「解体しないで現状のままの売却値段」と「解体しての更地にしての売却値段」がトータルではあまり変わらないこともあるからです。
その大きな理由に、購入者が建物建築と解体工事を行うと割安な解体工事費になることも多いからです。
また特にプロの建売業者が買う場合の解体費用は一般の方よりもかなり安く解体できます。
築古でオンボロの実家の場合、プロの建売業者が買い取って新たに新築住宅を建てて販売することが少なくありません。
その場合、素人が依頼した解体費用より毎回何度も発注している建売業者でとても大きな差が出てきます。
このあたりの事情はご理解いただけると思います。、
また解体工事は最低でも軽く100万円以上のまとまった金額になり、その費用を誰が負担するのか?
これもよく兄弟でもめてしまうポイントでもあります。
相続した実家を空き家のままで放置していませんか? 放置された空き家の実家はとても危険でご近所さんも大迷惑しているんです! そんなお悩みの方も少なくありません。 相続した空き家の実家の解体費用を兄弟でどう負担すればいいのか …